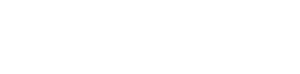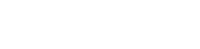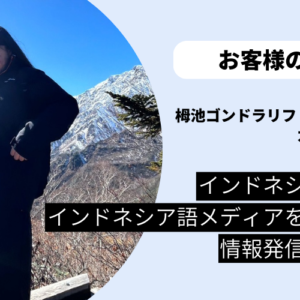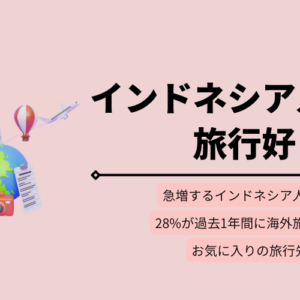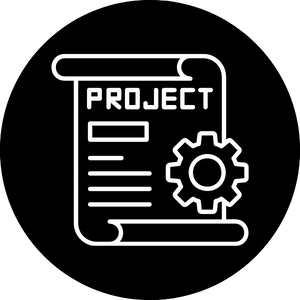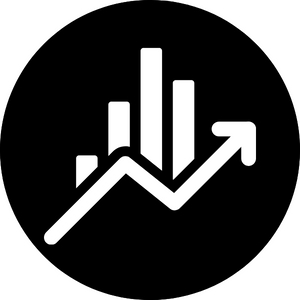カンヌを筆頭に、世界には有名な広告祭が複数ありますが、
インドネシアのケーススタディに出会うことはまだまだ容易ではありません。
一方、当然ですが国内では企業が凌ぎを削って広告活動を展開しています。
そして、日本と同様、インドネシア国内にもローカルな広告祭が存在しています。
その名もCitra Pariwara(英語でadvertisement image)。

今年の11月にフィナーレを迎えました。
日本語はもちろん、英語での情報もまだ多くはありませんが、
Campaign誌のレポート記事(2014/12/9)によれば、
・過去にも開催されているが、審査員のクオリティが低く、イベント自体の運営オペレーションも低レベルであったため、いまいち盛り上げりに欠ける状況が続いていた。
(そして、インドネシア国内のクリエイティブが世界レベルに到達しない一因でもあった)
・JWT JAKARTAのCEOであるLulut Asmoro氏に運営を委託し、運営は改善、今年は例年にない成功を納めた
ということです。
筆者も興味があり、調べてみました。
どのような作品が受賞しているのか?その中からいくつかピックアップします。
■RADIO 部門
HAPPY WIFE, HAPPIER HUSBAND.
なんと、Neo Hormovisionという男性向け精力剤のラジオ広告です。
妻の機嫌が良ければ夫の願い事も受け入れられ、夫はもっとハッピーになる、というシンプルな内容。
広告の内容そのものよりも、イスラム教主体であるこの国で、
夫婦の営みをテーマとしたコミュニケーションが受容されている事実が興味深いです。
(最近では都市部を中心に、価値観が変わってきた、という話も聞きますが)
フィルム作品も発見しました。
この、見るからに付け髭のダンディーな男性・・・癖になります。
■DIGITAL 部門
BLOOD BOOK

インドネシア赤十字社の献血をテーマとしたFacebookアプリケーション。
インドネシア人はSMSやEmail、Facebook Postからの献血リクエストに対して懐疑的であるが、
既知の友人伝手であればアクションを起こしやすい(担当エージェンシー談)ということから開発したようです。
蛇足ですが、インドネシアのFacebookユーザーは6900万人を突破しており(2014/6/28,Wall Street Journal)、
米国、インド、ブラジルに次ぐ世界4位の利用者数を保持しています。
また、人口が2.4億人もいるのでまだまだ伸びしろがある、とも言われています。
ただ、他国同様Facebook離れも顕著です。
統計データは手元にありませんが、筆者の知人達もそこまで頻繁には使っていないようです。
最近だとPath、そして我らが日本のLINEが人気です。
特に企業のプロモーションにおいてはLINEが活用されています。
来年どのように推移していくのか、気になるところですね。
■FILM 部門
TREE OF LIFE
Unilever Indonesia が展開するLifebuoyというハンドソープブランドの広告です。
HELP A CHILD REACH 5、と呼ばれるコミュニケーションプロジェクトの一貫のようです。
HELP A CHILD REACH 5(Youtube channel)
我々日本人からは想像がつかない話ですが、
世界では毎日5000人の赤ちゃんがハンドソープで防げる程度の感染症にかかり、
5歳未満で死亡しているそうです。
インドネシアは決して衛生環境が良い国ではなく、
医療レベルも低いですからまさに該当エリアの1つなのでしょう。
LifebuoyのWebを見ると、製品需要形成のための様々な啓発活動を展開しています。
話を広告に戻します。
ムービーが伝えたいことは、
石鹸を使うことによってこのような悲劇を減らすことができる、だからハンドソープ使おうね、ということですが、
共感の作り方(映像の表現)が優れていると思いました。
手を洗わないと雑菌が●●万匹も残ってしまいます!というアカデミックな話は
相手が誰だろうとあまり伝え方は変わりませんが、理屈だけでは人は動かないので感情も動かさねばなりません。
石鹸のような生活必需品は、都市部だけではなく小さな島々まで広めなければなりません。
そして、インドネシアは島ごとに多様な人種がおり、彼らの文化や風習に沿った表現が必要、ということかと思います。
ちなみに、本ムービーの解説によれば、
インドネシアの一部の民族は「赤ちゃんが生まれると木にマークする」という風習があるそうです(インドネシアは超多民族国家です)。
ターゲット層にはスマフォが普及していないのにWeb動画はどれくらい有効だったのだろう?と、
気になる部分もありますが、そのあたりはもちろん他の施策と組み合わせているのでしょう。
ざっと気になった作品をご紹介しましたが、
上記以外の作品についても、こちらから閲覧可能です。
http://www.citrapariwara.org/penghargaan
最後に少しだけ感想を。
筆者の出自がPR業界ということもあるのですが、
Unileverの事例にあったような啓発型コミュニケーションの可能性を大きく感じます。
「ジャカルタは都会」と本ブログでも伝えていますが、
それでも足りないものがまだまだ多い。
郊外に行けばさらにその傾向は強まるでしょう。
ジャカルタのような都会では生活をより楽しく・豊かにしてくれる商品やサービスが、
郊外では衛生的な生活を実現する一般消費財が、今後ますます求められます。
その際には、必要性を提唱し、理解者と共に商品自体を広げていくような
PRベースのコミュニケーションが求められるのだと思います。
大統領も変わり、世界からの注目も高まるインドネシア。
来年はどのような変化が生まれ、どのような製品・サービスが広まっていくのか、今から楽しみですね。
また、本年のCitra Pariwara開催成功をきっかけとして、
インドネシア国内のコミュニケーション業界が盛り上がることを期待して筆をおきます。