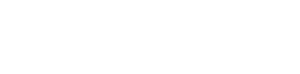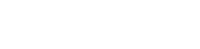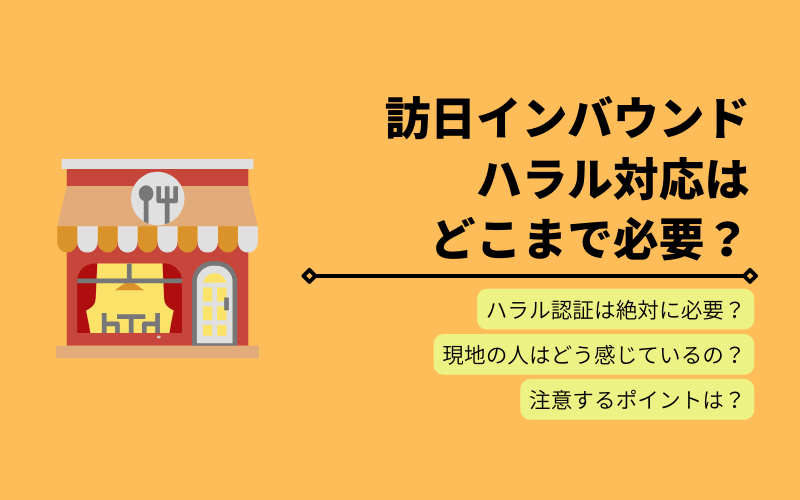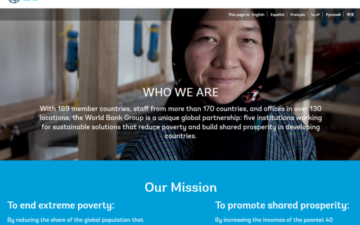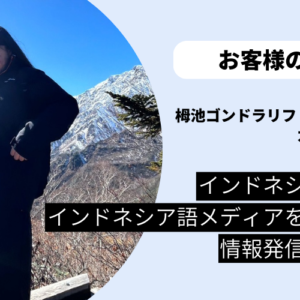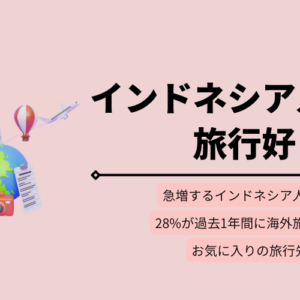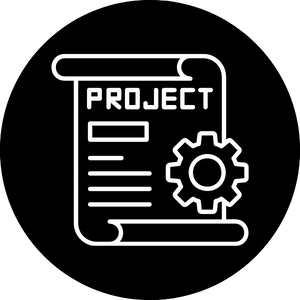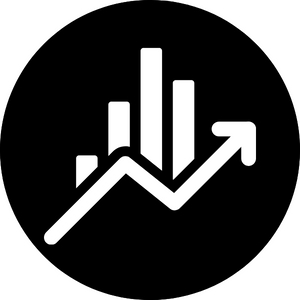人が移動できる世界が戻りつつあり、観光業は活気を取り戻しています。当社のブログでも訪日インバウンド市場の発展に役立つような情報を積極的に発信していきます。
今回は「ムスリム(※1)対応」、特に「飲食店のハラル対応」について書きたいと思います。
以下のような背景があります。
先月(2023年2月)にジャカルタで久しぶりにJFT(Japan Travel Fair)が開催されました。当社も某市のサポートとして入らせていただき、多くのインドネシア人観光客や旅行代理店の方々と話す機会がありました。
中でもムスリムの方々やムスリム専門の旅行代理店と話した内容の学びが深かったので、発信していきたいと思った…という次第です。
タイトルに「インドネシア編」と書いたのは国によって多少考え方のバラつきがあるからです。インドネシアのムスリムは完全なイスラム教国の他国と比べて「寛容(※2)」と言われることが多いです。それでも共通する部分、参考になる部分はあるでしょう。
それでは本題に進みましょう。
※1:イスラム教徒の総称です。
※2:ここでは「敬虔・厳格」の反対の意味です。
ハラルである、とはどういうことか?

画像引用:pixabay
訪日インバウンド×ムスリム、となった場合に一番に上がるテーマは「食のハラル」でしょう。そもそも食に関して「ハラルである」とはどういうことなのでしょう?
一般的には「酒を使ってない」や「豚を使ってない」と言われることが多いですよね。実際はもっと細かい規定がありますが、ここでは触れません。
それでは「ハラルか否かの判断」はどうすれば良いのでしょう?
ムスリムの方に「これ(この店)はハラルですか?」と聞かれた時にどのように判断するのか?
この問いに対する答えは一つで「ハラル認証があるかないか」です。
ハラル認証がないレストランや食べ物に対して、私たち外国人が勝手に判断するのは危険です。
と言いますのも、成分表を見ても細かい添加物の内容判断は外部からはできません。
さらにその商品自体が成分的にハラルだったとしても、同じ調理場や工場でハラム(ハラルではないもの)なものを製造・調理していればアウトです。
また、肉を使用する場合は、そもそも使用される肉がハラル肉(ムスリムによるムスリムのやり方に則って処理された肉)でなければハラルとは言えません。
上記の理由より、個人的に「大丈夫、これはハラルだよ」と言い切ってしまうことはできませんし、してはいけません。
ムスリムを呼び込むためには飲食店のハラル認証が必要なのか?

画像引用:Unsplash
それではムスリム観光客の対応をするために、飲食店は「ハラル認証」を取得する必要があるのでしょうか?
これは「YES」とも「NO」とも言い難い質問です。
ただ「ハラル認証がないとインドネシアのムスリムは来てくれないのか?」という質問に対しては明確に「NO」と言えます。
少し補足します。
大前提として「ハラル認証」を取得した飲食店の選択肢が多いに越したことはありません。認証(※3)がついていればムスリム側は安心して食べることができます。
しかし現実的に多くの飲食店がハラル認証を取得するのは難しいでしょう。
店舗がハラル認証を取得するためには、店舗単位でムスリム向けに仕様変更する必要があります。
レシピにメニューに食材、キッチンまですべてを変えなければなりません。費用も時間もかかりますし、今いる日本の顧客が離れてしまう可能性もあります。
そこで知っておきたいのがムスリムフレンドリーとモダンムスリムについてです。
※3:「ハラル認証の種類」についてよく聞かれますが、ことインドネシアについてはどこのハラル認証でもあまり気にしません。この辺りはまた別の機会に触れたいと思います。
ムスリムフレンドリーという考え方

画像引用:Pixabay
「ムスリムフレンドリー」という言葉はコロナ前から日本でも使われるようになりました。簡単に言うと「ハラル認証はないが、可能な範囲でムスリムの方々に配慮した対応を取り、適格に情報を開示する」ことです。
ムスリムの中には「ハラル認証付きのものしか食べない」という方もいれば、「認証が必ずしもなくとも、ある程度は自分で判断して食べる」という方もいます。
後者のムスリムの方は主に以下のような点を気にします(特に多い項目をピックアップします)。
- 食べたいメニューのレシピ自体に豚やラードが入っていないか
- 食べたいメニューのレシピ自体に味醂や酒などアルコール由来の調味料を使っていないか
- 食卓におかれている醤油はハラル醤油(アルコールなし)か
- 食べたいメニュー以外のメニューで豚やアルコールを使用しているか
- 調理場や調理道具はノンハラルと分けられているか
ムスリムフレンドリーにしたからといって、すべてのムスリムに受け入れてもらえるわけではありません。
またムスリムフレンドリーを受け入れる方々の中でも厳格さにはバラつきがありますから、個人によっては「この場合はOK」、「この場合はNG」と分かれます。
それでもムスリムフレンドリーのお店が増えることにより、一部のムスリムがその土地に訪れやすくなることは間違いではないでしょう。
モダンムスリム

画像引用:pixabay
もう一つ知っておきたいのは「モダンムスリム(インドネシア語だとMuslim Modern/ムスリムモデレンと発音)」という考え方です。
学術的な言葉の定義に踏み込むと非常に深い話になります。ここでは「イスラム教義に沿いながらも、比較的柔軟に様々なことを楽しみたいと考えている人達」程度で捉えておいてください。
先日のJTF期間に我々が訪問してきた旅行代理店も、ムスリムの中でもモダンムスリムと呼ばれるお客様を中心に扱っている会社です。
厳格なムスリムを相手にする旅行会社では、完璧なハラルツアーしか扱っていません。ハラル認証のあるお店だけを訪れ、さらに礼拝の時間も完璧にツアーの中に組み込まれて…という具合です。
今回訪れた旅行会社ではツアー構成がもう少し柔軟に組まれています。レストランはムスリムフレンドリーのお店、礼拝は一日一回はきちんとしたモスクを訪れるがそれ以外は組み込まない(参加者個人にゆだねる)、などが異なります。
彼らは日本に対する理解も深く、彼らの中で明確にこれはOK、これはNG、という判断基準がありました。この辺りはまた別の機会にまとめたいと思います。
最後に
理想ばかり追いかけても現実が動かないことは多々あります。
訪日インバウンドにおいては完全で完璧なムスリム対応(=ハラル対応)が理想ですが、日本の状況を考えると現実的には難しいでしょう。
ただ、放置もできません。経済成長著しい東南アジアには、インドネシアやマレーシアといったムスリムが多い国も含まれています。世界的にもムスリム人口は増加しており、2050年には世界人口の3分の1がムスリムになるとも言われています。
そこで重要になるのがムスリムフレンドリーという考え方です。この領域はなかなか厳密に定義できるものではありません。それゆえに教科書もありません。
教科書がない世界だからこそ現場の声を聞きながら作るのが重要です。
またその際は日本にいるムスリムだけではなく、実際のターゲットとなる現地ムスリムの声を聞くことが肝要です。
特に「どうすれば的確に伝わるのか?」という部分は現地に住んでいないとわからない点でしょう。
当社ではムスリムに対するプロモーションや調査のサポートが可能です。
また現地ムスリムのメンバーを交えた「ムスリム対応に関するオンラインプロジェクトチーム」の発足なども可能です。
ご利用の際はお気軽にご相談ください。